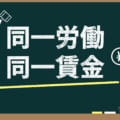【主張】監督実施へ体制の拡充を
法定労働条件の確保を使命とする労働基準監督官の業務がまたもや拡大するようだ。
政府がまとめた「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」の取組みの1つに、労務費などの価格転嫁徹底に向けた労働基準監督署の活用が挙がっている(関連記事)。過労死につながりかねない違法な長時間労働を是正するなど、労働基準関係法令の遵守に向けた指導が引き続き着実に実施されるよう、人員体制の充実を望む。
現在、全国に3100人余りの監督官が配置され、労働時間や休日、賃金支払いなど法定労働条件の確保をめざし、年間約14万件の定期監督等を実施している。労働者からの申告に基づく監督や、是正勧告実施後の再監督を加えると、17万件に上る。
他方、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の5日取得の義務化、同一労働同一賃金などを定めた働き方改革関連法の施行以降、監督官や労基署の業務の幅が広がっている。令和4年には、同一労働同一賃金の遵守徹底を実現するため、労基署がチェック表を用いて事実確認を行う取組みを開始。また、運送事業者に仕事を依頼する荷主や元請運送事業者には、荷待ち時間解消に向けた要請を行うとともに、貨物自動車運送法に基づく「標準的な運賃」の周知を図っている。
政府がこのほど打ち出した賃金向上推進5か年計画は、実質賃金の上昇をめざし、省力化投資や、労務費などの価格転嫁を後押しするもの。サプライチェーンの隅々まで価格転嫁を浸透させるために、労基署が新たに、監督指導などの機会を捉え、労務費転嫁指針の活用など賃上げ原資確保に向けた働き掛けを開始するという。
監督官が対応すべき事案は、働き方の個別化・多様化を背景に複雑化が進んでいる。そうしたなかで、担う役割・業務が広がりすぎれば、本来の監督指導業務にも悪影響が出かねない。
厚労省は今年度、AIを活用した効果的・効率的な監督指導の実施に向け、DX推進態勢を強化している。監督手法の効率化と並行し、必要な人員の確保も求めたい。