はご利用いただけません。
安全対策の決め手できる職長の実務必携
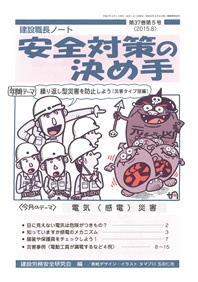
これを知れば作業者を災害から守れる!
現場の責任者である職長が、多岐にわたる日常業務の中で最も配慮しなければならない災害防止。
わが国を代表する大手建設業各社の安全担当責任者が執筆陣として、年間の統一テーマを決定したうえで、災害防止のノウハウを開陳します。
安全対策の要点がひと目でわかるようイラストを多用し、現場の責任者にマッチした分かりやすい解説で、安全衛生教育のテキストとして最適です。
- A4判・15ページ
- 月1回(1日付け)発行
- 購読料(税込):13,200円(年間)
安全対策の決め手 2024年度
2024年度の年間テーマ
『災害事例を学び、墜落転落災害を防ごう!』
墜落転落災害は、休業4日以上の事故型別災害統計で最も多い災害です。墜落転落災害を防ぐことが災害減少に最も効果があると言われています。今年度は、この墜落転落災害を減少させるため、災害事例から安全管理のポイントを学んでいきましょう。
- 第1号:4月
- 床端部からの墜落転落防止
- 第2号:5月
- 足場からの墜落転落防止(組立・解体時を含む)
- 第3号:6月
- 鉄骨からの墜落転落防止(デッキ作業を含む)
- 第4号:7月
- 可搬式作業台・天台等からの墜落転落防止
- 第5号:8月
- 屋上・屋根からの墜落転落防止(スレートを含む)
- 第6号:9月
- ダメ穴、ピット開口からの墜落転落防止(地中梁鉄筋上を含む)
- 第7号:10月
- 建設機械・車両系建設機械からの墜落転落防止
- 第8号:11月
- 作業構台・荷取り開口からの墜落転落防止
- 第9号:12月
- 階段からの墜落転落防止
- 第10号:1月
- 高所作業車・ローリングタワー・高所作業台からの墜落転落防止
- 第11号:2月
- 山留・立坑・法面等からの墜落転落防止(切梁を含む)
- 第12号:3月
- トラックの荷台、集積した資機材からの墜落転落防止
安全対策の決め手 2025年度
2025年度の年間テーマ
『職長の役割を再確認し、災害を未然に防ごう!』
災害の発生を防止するには、安全衛生のキーマンである職長が果たす役割が大きいです。そこで、職長が果たすべき役割を再認識していただき、災害の発生を未然に防止することにお役立てください。
- 第1号:4月
- 職長の責務の実践
- 第2号:5月
- 熱中症災害の防止
- 第3号:6月
- 作業者の健康管理と通勤災害
- 第4号:7月
- 保護具の指導、点検・確認
- 第5号:8月
- 業務上疾病の防止
- 第6号:9月
- 作業手順の作成と現地確認
- 第7号:10月
- 作業終了時の点検・確認
- 第8号:11月
- 2m以上の高所からの墜落・転落災害防止
- 第9号:12月
- 車両系建設機械による災害防止
- 第10号:1月
- 感電災害・火災の防止
- 第11号:2月
- 電動工具による災害防止
- 第12号:3月
- 高齢者・未熟練者・外国人労働者の災害防止










