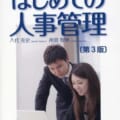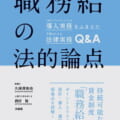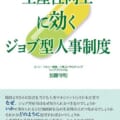- 2025.07.24 【主張】
-
【主張】新人定着へ能開主義回帰

人手不足の解消というより新陳代謝を急ぐ有力企業によって、新卒採用市場は今やVIPルームと化した。20万円台半ばの初任給は最低レートとして高過ぎるし、インターンシップによる先行投資も、付け焼刃ではリターンが望めない。従来以上に新人をいかに定着させ、育て上げるかが問われるなか、一部では能力開発主義を強化する取組みも増えてきている。 福祉用……[続きを読む]
はご利用いただけません。