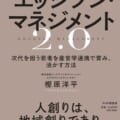【主張】学生の就業体験活性化を
3日以上の就業体験を含む“新たなインターンシップ”に参加した大学生・大学院生は3万人強――文部科学省はこのほど、「学生のキャリア形成支援活動」に関する調査結果を公表した。産学の協議会(採用と大学教育の未来に関する産学協議会)がインターンシップなどの要件を改めて定義して以来初の調査で、全国の大学810校などに令和5年度の実施状況を尋ねたもの。“新たなインターンシップ”とされたタイプ3=「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」の参加者数は、大学が単位認定する活動で2万3000人弱、単位認定しないが参加状況を把握したり、関与している活動では7700人強だった。
両者を合わせた約3万人という数字は、当時の大学在学者数(294.6万人=令和5年学校基本調査)の約1%に留まる。学部1~2年生が対象外であることを差し引いても、初年度から広く活用されたとは言い難い。産学協議会では、募集要項に記載できる「準拠マーク」を配布するなどしており、今後の普及が待たれる。
タイプ3の要件については、①実施期間が5日間以上(専門活用型は2週間以上)、②うち半分を超える日数を就業体験に充てる、③職場の社員が学生を指導……など計5項目に及ぶ。産学協議会の定義では、これらを満たさない短期間のイベントや説明会(タイプ1)、企業による教育プログラム(タイプ2)などは、インターンシップに当たらない。質の高い取組みの普及をめざす意図には頷けるものの、実施企業には相応の体力が求められる。
学生を受け入れ、指導する各職場の負担はもちろん、企業によっては参加者の募集・確保が大きな課題にならざるを得ない。地方に本社を構える大手・中堅企業からは、むしろ学生側のニーズは多様で、短期開催を望む声もあるとの指摘が聞かれる。
今後も生産年齢人口の減少局面が続くなか、若手の確保は個々の企業の問題に留まらない。人材流出に悩む地域にこそ、産学官の連携を通じたインターンシップの定着・活性化が期待されよう。