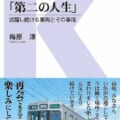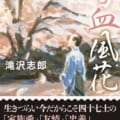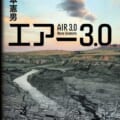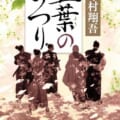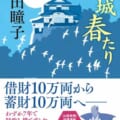【書方箋 この本、効キマス】第116回 『メンターになる人、老害になる人。』前田 康二郎 著/内田 賢
相手への敬意が分かれ道
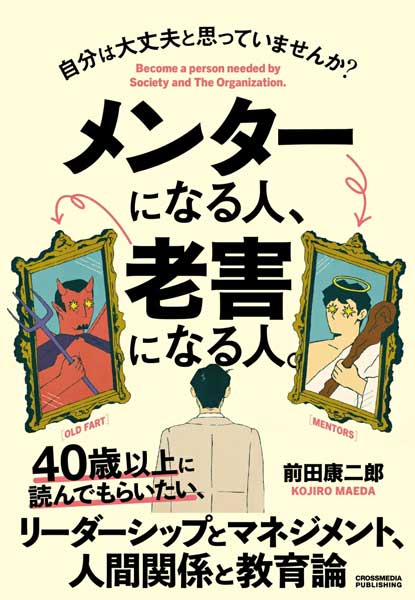
大手機械メーカーの総務部長を役職定年で退いたK氏は「部長でなくなったら、いろんな人間が相談に来るようになった」と話してくれた。ざっくばらんな方なので部長在任中もいつでも相談に乗ってくれた人であろうが、業務時間中に若いヒラ社員が課長を飛び越して、また、他部門の課長が直属の部長に断りなくK部長に相談に来るのは憚られたであろう。かつての部長も今は無役、細かいことを気にする必要がなくなったので皆が気軽に相談に訪れ、多くの人たちの「メンター」になっているようだった。
高齢者雇用について従業員にアンケート調査をすると、自由記述欄は職場の高齢者に対するさまざまなコメントであふれる。「自分が世話になった職場の神様を会社はもっと大事にしてほしい」という肯定的コメントもあるが、「何でこんな人たちをいつまでも会社に置いておくのか」、「昔話ばかりして今の状況に適応しようとしない」など「老害」を訴える否定的コメントも多い。
職場には「メンターになる人」もいれば「老害になる人」もいる。そして我われはメンターになる素質を持つ人が「メンターになる人」、老害になる素質を持つ人が「老害になる人」と考えがちである。しかし、この本の著者である前田康二郎氏は「メンターになる人と老害になる人は紙一重」とする。「全く似ても似つかない別人格の人物を想像することでしょう。しかしそうではなく、老害を引き起こす人とメンターとして尊敬される人は実は同一人物の場合もあるのです」と氏は説く。では何が分かれ目なのか、それは「相手への敬意」を持ち続けるか失うかであるという。「立場の違いに関係なく双方が敬意を持ちながらコミュニケーションをとることが大切なのです」と指摘する。
本書は16章からなる。メンターや老害の特徴、老害が発生する環境、自分がメンターになるために心掛けること、老害になった人をメンターに変身させる方法、メンターを増やすための社風改善など、個人はもちろん職場や会社も考えるべき事柄が述べられている。読み始める前に9ページにわたる目次をまず眺めてほしい。たとえば第8章「老害とは縁遠いメンターの方達の特徴」は「メンターは他者の成功を喜べる、喜び慣れしている」、「メンターは支えようとしてくれる」、「メンターは共感してくれる」、「メンターは出し惜しみせず知識や知恵を授けてくれる」などのパートからなり、それぞれがワンポイントアドバイスとなっている。
自覚がなくてもすでに職場の老害になっているかもしれない、今は多くの同僚に慕われていても思わぬきっかけで老害に変身するかもしれない。職場はもちろん家庭や地域でもメンターとして周囲を支援できれば他者も自分も幸せになれる。メンターがこれからもメンターであり続けるために、また、これからメンターに変身するために、本書を読んで「メンターへの道」を実践してみてはいかがだろうか。
(前田 康二郎 著、クロスメディア・パブリッシング 刊、税込1738円)

東京学芸大学
名誉教授 内田 賢 氏
選者:東京学芸大学 名誉教授 内田 賢(うちだ まさる)
専門は人的資源管理論。55歳定年時代の1980年代から企業の高齢者雇用の調査研究に従事している。
濱口桂一郎さん、大矢博子さん、そして多彩なゲストが毎週、書籍を1冊紹介します。“学び直し”や“リフレッシュ”に是非…。