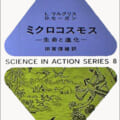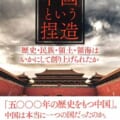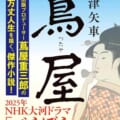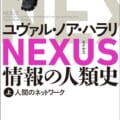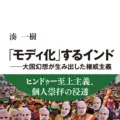【書方箋 この本、効キマス】第110回 『松浦武四郎 入門:幕末の探検家』 山本 命 著/吉田 修
蝦夷を記録した“兼業者”

松浦武四郎は、16歳で故郷伊勢を離れ、日本を隈なく歩き、唐・天竺まで渡ろうと志を立てた。その後、ロシアの脅威を知るに至り、蝦夷島に渡り、原野に分け入り、樺太にまで足跡を残し、その克明な記録を世に紹介した。北海道の名付け親としても知られている。著者の山本命氏は、三重県松阪市にある松浦武四郎記念館の館長である。
武四郎は現代風に言うと、国家公務員でありながら、プロアドベンチャーレーサー&蝦夷地フィールドワーカー、ノンフィクションライター、漫画家&イラストレーター、骨董コレクター、江戸・明治期のYouTuber等々を兼業するノマドワーカーであった。究極のマルチ・ジョブ・ホルダーなのだ。筆者憧れの人物でもある。
彼の主要な業績を挙げてみよう。1つ目は探検家。若くして全国を歩き、見分を広めた。蝦夷地については、28~32歳までは個人として3回、39~41歳までは幕府のお雇い役人として3回調査している。その範囲は蝦夷地の内奥や国後・択捉・樺太に及ぶ。現在でも武四郎を顕彰する石碑などが道内に50基以上あるという。また、彼は北海道から九州まで数多くの山を登った近代登山のパイオニアでもあった。
2つ目はルポライター・出版人である。北海道の地名9000をインタビューによって収集し、1万キロメートルを踏破した武四郎は、文も絵も達者であり、『東西蝦夷山川地理取調図』、『アイヌ人物誌』などおよそ150冊の調査記録書を遺している。それも自費出版によるものが多い。
特筆すべきは、元治元年に、自ら作成した蝦夷地を理解するためにまとめた『新版蝦夷土産道中寿五六』である。振出しは函館湊で、各マスには、地元の山・川・名産物が多く記載されているが、私娼とその名前も記載されている。双六を誰にでも分かりやすいメディアとして活用したのである(本双六は築地双六館DBから検索できる)。
3つ目はヒューマニスト。彼の旅日記には、アイヌ民族に対する松前藩の非道な圧政が度々記されており、そのために数々の妨害工作に遭い、刺客にもつけ狙われた。アイヌへの思いは、「こころせよ えみしおなじ人にして この国民の数ならぬかは」との言葉にも表れている。
4つ目は人脈ネットワーク。「情報量は移動距離の二乗に比例する」という言葉があるが、当時、歩行による生涯移動距離が随一だった武四郎は、全国の著名人と交わりがあった。藤田東湖、頼三樹三郎、箕作阮甫、吉田松陰、大久保利通、西郷隆盛、木戸孝允、岩倉具視など。彼の蝦夷地の知見の賜物であろう。嘉永7年に松陰が訪ねてきた際は、1つの布団に枕を並べて国防論を交わしたという。
自ら足と目で見たものだけを信じ、記録し、世に知らしめることをもっぱらとして生きた武四郎は、インターネットやSNSが覇権を持つ現代の世相を如何に見るのであろうか。
(山本 命 著、月兎舎 刊、税込1320円)

築地双六館 館長 吉田 修 氏
選者:築地双六館 館長 吉田 修(よしだ おさむ)
リクルートや全国求人情報協会に勤務。1995年から双六の収集を開始し、在職中の2000年に築地双六館を設立。昨年、立命館大学ARCとの共同プロジェクトで双六DB(データベース)を公開した。
濱口桂一郎さん、大矢博子さん、そして多彩なゲストが毎週、書籍を1冊紹介します。“学び直し”や“リフレッシュ”に是非…。