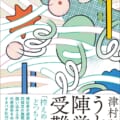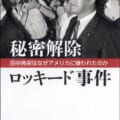【書方箋 この本、効キマス】第120回 『青春は美(うる)わし』 ヘルマン・ヘッセ 著/林家 彦三
この本とともにカルヴへ
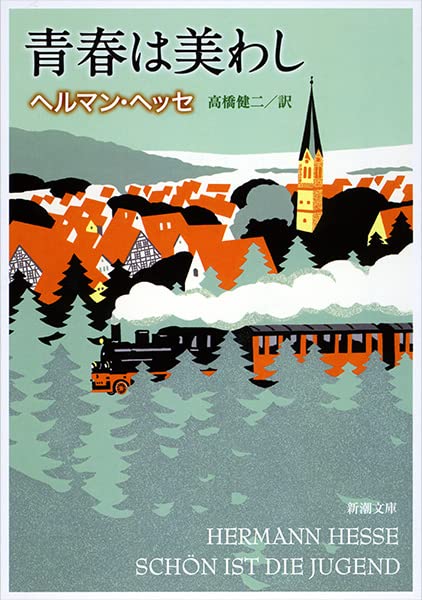
夏になると私は、新潮文庫の氷菓子色の背表紙に手を伸ばす。そして私は毎夏、汽車に乗り、小さな町に帰省する。プラットフォームに懐かしいエニシダの茂みを認め、見おぼえのある屋根屋根の区別をつけ、その中の煙突からコーヒーをわかす、あたたかい青い煙を見る。そしてマテーウスおじに再会し、握手する。それからさっぱりとした服と、こと欠かないだけの下着類と、数冊の本と、二本の美しいパイプの入っている茶色のカバンを開ける。頼れる父と信心深い母と、妹と弟と、オウムのポリーが私を迎える。それからむかし恋したことのあるヘレーネ・クルツと、妹の女友達であるアンナ・アンベルクに会う。そして私は、毎夏、この小さな町で、失恋をする。
その道順は変わらない。私はその間に、妹のピアノでシューベルトのリートを歌い、弟の花火の仕掛けづくりを手伝い、夜には小さい石油ランプを点けて、ジャン・パウルの美しい小説を読む。チンドン鳴らして町にやってきたどさ廻りの道化役者の大道芸を見て、あこがれと、かなしみと、癒しを得る。二人の少女を連れて、小川沿いにある夏の料理店で、コーヒーとアイスクリームとお菓子を振る舞うために、古い歌を歌いながら、山道を歩く。その途中の岸辺で、少女の一人と、カワラナデシコの大きな花束をつくる。
すべては、変わらない。ただそれは印字されているだけの言葉の連なりである。変わった方は、私だ。それでも私は夏になると、必ず、新潮文庫の氷菓子色の背表紙に手を伸ばす。そして、失恋をする。また明日、働くために。新しく出会うために。あらゆる別れを、美しくするために。
小説とは、そのためにあるのかもしれない。実用書やガイドブックも良いけれども、そういう種類の活字では捉えきれない、空想上の、透明な、その動作は変わらない、覗きからくり。一つの舞台があって、異国が舞台ならば異国風の、いくつかの単語があって、そこで私たちは、いつも同じ人物に再会する。それは私たちの実人生に、微妙な線引きをなしながら展開する、大きな外側の世界をなぞるための、先人が編んだ、大きな花束である。
この作者は、ドイツ南西部の谷あいの町、カルヴに生まれた。私は落語家だがドイツ文学かぶれという星のもとに生まれて、学生の頃、一度ボンに短い留学をしていたことはあるが、私淑するこの作家の故郷にはまだ足を運べていない。いつか行ってみたいと思うが、その時は、私はこの小説をカバンに入れるだろう。さっぱりとした服や、こと欠かない下着類と一緒に。
しかし、ドイツは遠い。それでも私たちは、小説と同様、常にある種の自由を得ている。私は先日、自身の郷里の田舎町で束の間の夏季休暇を過ごしたが、その時に自然の中で、ヘッセを旅の友に、ドイツが故郷なのか、故郷がドイツなのか、という身勝手な、美しい勘違いの中で過ごした。この花束には、送り先の指定も、飾り方の決まりもないのである。
(ヘルマン・ヘッセ 著、高橋 健二 訳、新潮文庫 刊、税込473円)

噺家 林家 彦三 氏
選者:落語家 林家 彦三(はやしや ひこざ)
福島県出身。2015年に林家正雀に入門、20年に二ツ目昇進。著書に『汀日記』、『猫橋』シリーズなど。
濱口桂一郎さん、大矢博子さん、そして多彩なゲストが毎週、書籍を1冊紹介します。“学び直し”や“リフレッシュ”に是非…。