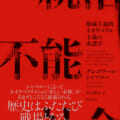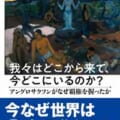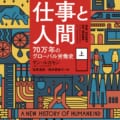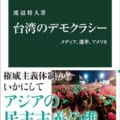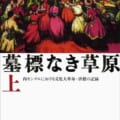【書方箋 この本、効キマス】第118回 『テクノ封建制』 ヤニス・バルファキス 著/濱口 桂一郎
デジタル領主が権力駆使
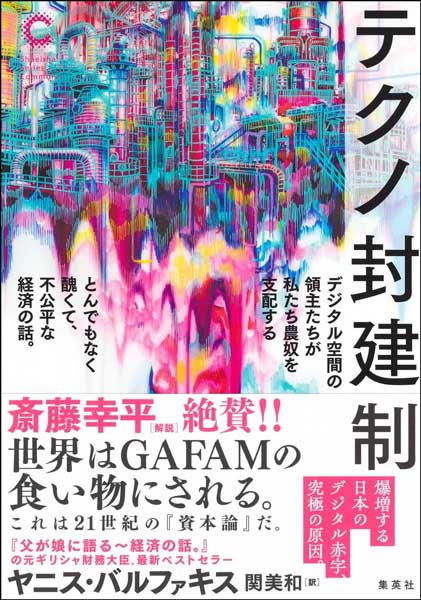
著者はギリシャの政治家・学者で、経済危機時に財務大臣になり、債務帳消しを主張したことで有名だ。本書の語り相手に設定されている父親譲りの左翼で、資本主義がやがて社会主義にとって代わられることを夢見ていた。ところがあに図らんや、とって代わったのは社会主義ではなくテクノ封建制であった。
テクノ封建制とは何か。資本主義とどう違うのか? 資本主義は、資本家が資源や労働力を活用(搾取)して生産活動を行い、利潤を生み出す。だから、資本家と労働者の対立が社会の基本対立図式になるし、生産活動の場で労働者が団結して資本家と対決し、労働者の利益を拡大する社会をめざすことも可能であった。ところが、テクノ封建制ではすべてがひっくり返ってしまう。
テクノ封建制を支配するのは生産手段を所有する資本家ではなく、プラットフォームと呼ばれる需給をアルゴリズムでマッチングする「場」を独占するクラウド領主たちだ。GAFAMと呼ばれるごく少数の領主たちは、そこに商品を出品する封臣資本家に対しても、労務サービスを提供するクラウド農奴に対しても、絶対的な権力を有する。プラットフォームへのアクセスをスイッチオフするだけで、彼らはあらゆる商品・サービス需要へのアクセスから遮断されてしまうのだから。売るためには領主さまに従わなければならないのだ。その絶対的権力を駆使して、クラウド領主たちは莫大な「利用料」を巻き上げる。これはもはや資本主義的な「利潤」ではなく、経済学的には「レント」(地代)に属する。「利潤」が(労働者を使った)資本家による生産活動によって生み出されるのに対し、「レント」は他人に生産活動を行わせて、その上がりをわがものにするだけだ。その姿は、かつて中世封建社会で、武力を振りかざして年貢を巻き上げていた領主たちと変わらないではないか、というわけだ。
筋金入りの社会主義者のはずのバルファキスが、資本主義の大明神たるアダム・スミスを引っ張り出してこんな愚痴を語らせるというのが、何とも皮肉の極みであろう。曰く、「スミスがスコットランド訛りで嘆く声が聞こえてきそうな気がする。2008年以降、資本主義救済の名目で、中央銀行は資本主義のダイナミズムとその利点を抹殺した。有害な封建的地代まがいのものが蘇って、実り豊かな資本主義的利潤に対する歴史的な復讐を果たす機会を得たことに、スミスは落胆しているだろう。利潤の追求は哀れなプチ・ブルジョワに委ねられる一方で、本当の金持ちは、『負け犬が利潤を追い求めているぞ』と嬉しそうに囁き合っている」。
いまや世界でクラウド領主がいるのはアメリカと中国だけだ。EUも日本も、利潤追求の資本主義時代にはアメリカを追いつめるほどに威勢が良かったが、現在は哀れな負け犬として、一生懸命生産活動で稼いだ利潤を領主さまに巻き上げられる一方だ。彼に言わせれば、米中対立の真の姿は、どちらのクラウド領主が世界を支配するかという死闘なのだ。
(ヤニス・バルファキス 著、関 美和 訳、集英社 刊、税込1980円)

JIL-PT 労働政策研究所長 濱口 桂一郎 氏
選者:JIL―PT労働政策研究所長 濱口 桂一郎
濱口桂一郎さん、大矢博子さん、そして多彩なゲストが毎週、書籍を1冊紹介します。“学び直し”や“リフレッシュ”に是非…。